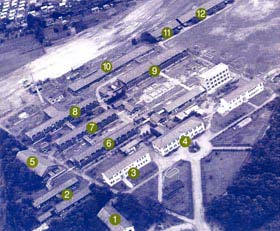| 2001(平成13)年 |
|
| 3月 2日 |
東京大学史史料室中野実助教授来室 |
| 5日 |
総務掛との話し合い(予算関係) |
| 7日 |
第13回編集委員会 |
| 9日 |
馬渡編纂委員長との話し合い(今泉室長、中川講師、高橋助手) |
| 12日 |
附属図書館より資料調査 |
| 15日 |
百年史編纂委員会(12年度事業報告、13年度事業計画、13年度予算)
編纂室スタッフ会議 |
21日
〜23日 |
大学アーカイヴスに関する研究会(於、京都大学)に参加(中川講師、史料館永田研究員) |
| 27日 |
工学部史編纂室員来室 |
| 29日 |
竹内峯名誉教授(理)来室 |
| 30日 |
『東北大学百年史編纂室ニュース』第7号発行
松崎啓三室員(事務補佐員)退職 |
| 4月 1日 |
久保内将雄室員(事務補佐員)採用 |
| 5日 |
経理部主計課との話し合い(部局史について) |
| 6日 |
経理部主計課との話し合い(部局史について) |
| 10日 |
事務局史編纂室との話し合い |
| 11日 |
経理部所蔵資料調査 |
| 12日 |
総務部総務課との話し合い(事務局史について) |
| 19日 |
工学部史編纂室員来室
企画調査室より調査依頼(産学協同について)
竹内峯名誉教授(理)来室
編纂室スタッフ会議 |
| 23日 |
工学部史編纂室員来室
竹内峯名誉教授(理)来室 |
| 27日 |
工学研究科鈴木睦教授、工学部史編纂室員来室(部局史関係資料閲覧)
編纂室スタッフ会議 |
| 5月 7日 |
今泉室長との話し合い(中川講師・高橋助手) |
| 9日 |
第25回百年史編集委員会幹事会 |
| 14日 |
教育学研究科所蔵資料調査(水原教育学研究科教授・中川講師、高橋助手、史料館永田研究員)
今泉室長との話し合い(中川講師、高橋助手) |
| 16日 |
歯学部事務部より任官表作成について照会 |
| 17日 |
教育学研究科より資料借用(中川講師・史料館永田研究員)
編纂室資料配置換え
元編纂室員小野和夫氏来室 |
| 18日 |
印刷業者との話し合い(編纂工程について) |
| 21日 |
経済学研究科より任官表作成について問い合わせ
第14回編集委員会(資料編ワーキンググループについて。部局史について) |
| 25日 |
学務部学生課との話し合い(部局史について) |
| 30日 |
経理部主計課・管財課所蔵資料の調査
編纂室スタッフ会議 |
| 6月 1日 |
学務部資料調査(中川講師・高橋助手・史料館永田研究員) |
| 4日 |
文学部史編纂室員来室(任官表作成について) |
| 5日 |
赤尾綱男氏(新制東北大学一期生)より資料受贈 |
| 25日 |
「東北大学史年表(第1版)」「部局史編纂のしおり(改訂版)」等の学内配布
編纂室スタッフ会議 |
| 26日 |
第1回資料編ワーキンググループ会議 |
| 27日 |
学務部留学生課所蔵資料の調査 |
| 28日 |
学務部留学生課所蔵資料の一部移管 |
| 29日 |
戦後教育資料(東北大学教育学部創設資料)マイクロ撮影開始 |
| 7月 3日 |
学務部史担当者との話し合い(部局史関係) |
| 10日 |
学務部学生課所蔵資料の一部移管 |
| 18日 |
資料編ワーキンググループ主査入間田宣夫教授との話し合い(中川講師・高橋助手) |
| 23日 |
第2回資料編ワーキンググループ会議 |
| 24日 |
文学研究科院生会関係資料調査(中川講師・史料館永田研究員) |
| 26日 |
学務部所蔵資料一部借用 |
| 27日 |
編纂室スタッフ会議 |
| 31日 |
医学部附属病院より任官表作成について照会 |
| 8月 2日 |
工学部史編纂室室員との話し合い(部局史について) |
| 9日 |
事務局経理部契約室との話し合い(『百年史』販売分の扱いについて)
加齢医学研究所より任官表作成について照会 |
| 14日 |
事務局より資料借用 |
| 17日 |
旧農学研究所関係資料の調査(中川講師・史料館永田研究員) |
| 20日 |
事務局総務課法制掛所蔵資料調査(中川講師・高橋助手) |
| 21日 |
印刷業者との話し合い(組体裁について) |
| 22日 |
経済学研究科より任官表作成について照会 |
| 23日 |
百年史の販売に関する参考資料を東北大学出版会に送付 |
| 24日 |
宮城県議会図書室調査(中川講師・高橋助手) |
| 27日 |
法学部法制資料調査室より広中俊雄教授旧蔵「東北大学の管理運営に関する資料」借用 |
| 29日 |
工学部史編纂室より任官表作成について照会 |
| 30日 |
編纂室スタッフ会議 |
| 9月 3日 |
東北大学百年史編纂室ホームページ公開 |
| 4日 |
戦後教育資料(東北大学教育学部創設資料)マイクロ撮影終了 |
| 5日 |
工学部史編纂室より任官表作成について照会 |
| 6日 |
総務部人事課所蔵資料調査 |
| 7日 |
印刷業者との話し合い(組体裁について)
玉懸博之名誉教授(文)来室(法文学部史関係資料調査) |
| 11日 |
総務課法制掛との話し合い(大学院重点化について) |
| 14日 |
第5回通史専門委員会(通史編の構成について) |
| 27日 |
編纂室スタッフ会議 |
資料調査を目的とした来室者(上記以外。カッコ内は回数)
事務局史編纂室(14)、事務局総務部(3)、学務部(41)、施設部(1) |