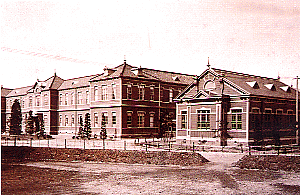▲ ニュースの目次へ
東北大学百年史に寄せて−西澤潤一先生講演要旨−
『東北大学五十年史』は、原田隆吉先生がお書きになったと聞いておりますが、大変名著であると思っております。古本屋に行ったら、数ある大学史のなかで、『東北大学五十年史』の値段が一番高かった、という話があります。
私がずっと感じておりますのは、東北大学の構成員が東北大学の歴史を殆ど知らない、つまり本学の特徴が掴まれていない、ということを非常に残念に思っております。私は学閥は大嫌いですが、学の伝統は大事にすべき
であると思っております。それは変えてはいけないというのではなく、磨きをかけていくことだと思っております。
各大学の研究のやり方というものは、みな特徴があって、どれが一番かということは、先になってみないと分からないわけでありますが、それが一本である必要はなく、何種類かの方法があってよろしいかと思います。とにかく、皆が磨きをかけて素晴らしい理想的なものに近づけていこうという学問の展開をしていかなければおかしいわけです。そういうところで見習った学生は、やはりそういうやり方をとるんだろうと思います。
たしか『科学エリ−ト』という本に、ノ−ベル賞受賞者の系列的分析がありますが、これによりますとノ−ベル賞受賞者は、圧倒的にノ−ベル賞受賞者の研究室から出ている確率が高い。その後に有り難いことが書いてありまして、ノ−ベル賞をもらってからついた弟子からはあまり出ていないが、ノ−ベル賞をもらう前についた弟子からはたくさん出ている。おそらく、先生はノ−ベル賞をもらうと忙しくなり、研究室にいなくなる。研究費もふえて、きわめて甘やかされた研究の仕方になるためではないかと思います。
本学においても、本多光太郎先生や八木秀次先生の周辺から大変な学者が出ました。素晴らしい先生のそばにいて、先生の背中を見ながら育っていくというのが本当で、その弟子の中に優秀なのがいて、そのまた弟子までが優秀になっていくのであります。
本学は「実学」とよく言われますが、現実との対応を絶えずとっていくというのが、サイエンスそのものであります。自然をよく見るというのが自然科学ですね。その中から一つの法則性を見つけ出してくる。寺田寅彦先生が鉛の中に鉛を食って生きている虫がいるという話を聞いて、一生懸命調べたという話がありますが、この寺田寅彦先生は、本多先生と同じようにグラスゴ−大学のケルビン卿の流れを汲んだ学者であると私は了解してお
ります。
学風というのは、ひとりでにつながっていくものですし、ケルビン卿のところでは、現実との対応を絶えずとりながら、自然科学の展開をやられました。これが奇しくも本学に、本多先生を通して流れてきた。本多先生が東大の物理学科から、その学風を一身に背負って本学にお出でになったことで、本学の創立以来の学風がいわゆる実学になった。産学協同だという人がいますが、私はそのようなものではないと思います。つまり学問のないところに入っていって、実際に現物と向き合って新しい学問を展開してきた。要するに中心は現物をよく見てやるというのが東北大学の学風ではないかと思います。本多先生は、東大工学部を創った人達とは明らかに違った
毛並みの先生のようです。いわゆる本当の意味での実学の展開をやってのけたのが本多光太郎先生であります。
自然科学というものは自然をよく見る、社会科学なら社会をよく見るというところから出発するのでありまして、そのなかにある一つの法則性を見つけ出し、さらに定量化するというのがサイエンスのオ−ソドックスな展開です。だから、何か難しい式を使わないとサイエンスではないという方がいますが、それは大変間違った考え方だと思います。
文系も、田辺元先生が理科大学の「科学概論」という共通の講義を担当されましたが、その後任の三宅先生も共に京都大学の哲学の教授となられました。極めてユニ−クかつ斬新な学問が本学から生まれたということを我々は考えるべきであります。本学では、山田孝雄先生をお呼びして神道の研究をやっていた。現実にあるものをきちんと研究するという態度から来ているものと思われる。そういう意味で、文系でも大変ユニ−クな展開をした。大変有名な木村亀二先生は、法解釈学ではなく法律をつくる学問をやっていらしたという話がある。
生物学の方もそうですね。野村先生は浅虫あたりのご出身ですね。その前が、オ−ストリ−から来られたハンス・モ−リッシュ先生でした。大変な学者ですが、第一次大戦後生活が苦しいためいろんな先生が日本にも来られました。加藤陸奥雄先生もそうですが、生態学が多いんですね。生物そのものの生き方を良く見るというところに生物学の原則があるということで、その方面の仕事が非常に多かった。
八木秀次先生は、東大を四、五番で卒業されました。大体大変な学者というものは、概して成績が悪いということが言われております。本多先生はトップだったそうですが、それでも成績は良くなかったらしいですし、大学院に入るのはやめた方がいいと、父親から思われたくらいです。鯨井先生という講師の方がいらっしゃいましたが、この先生が東大で一人だけで通信の研究を始めておられました。八木先生は、この先生から仙台に行ったらどうだといわれて、来られたようであります。
八木先生は仙台高等工業学校の先生として、ずっと待命しておられたわけであります。八木先生は雑誌会などを通じて本多先生と接触するうちに、こういう学問が一番いいんだということをお考えになりました。つまり、基礎と応用をぴったりとくっつけたんですね。それで、東北大学に工学部ができた暁には、今の理学部と工学部の間みたいな学問をやるべきではないかとおっしゃっていたんです。
そんな訳で、本多先生は応用までおやりになったのですから、工学部はいらないだろうという、変なところでとばっちりが出ているんです。結局しばらく遅れて、本当なら工科大学となったわけですが、その時期を失ったために、東北大学工学部は初めから工学部として出発することになったわけです。他の大学に比べると造船もなければ、建築もないという基礎オリエンテッドの展開をやったというのは、八木先生の、基礎科学に基づいた工学をやるということがこの特長の原因なんだろうと思います。
新制大学になるとき、高専などとの合併のため応用まで含んだ形になったわけですが、今で言うところの基礎工学部が東北大学にあったということなんですね。すぐ外国の後追いしていい気になる方がいますが、東北大学
の学風というのをご覧いただければ、そんな情けない後追いなんかやっていないですね。世界でもトップになるような新しい考え方をどんどん入れて展開してきた大学であることをぜひご記憶いただきたいと思います。
東北大学をつくるときに、理科大学と農科大学をつくろうとなったわけです。九州は重工業の中心ですから工学部と理学部でもって発足させて、東北大学は理学部と農学部でやろうとしたわけです。北海道に行って北海道
大学は昔は東北大学だったというと、いやな顔をするんですね。仙台よりも早く講義が始まったんだから、3番目にできた大学は北海道大学で、東北大学は5番目だというわけでありますが、これは大変めちゃくちゃな話で
あります。
八木先生も通信という分野で学生を養成され、研究業績も挙げられたわけであります。電気の先生方は、講義は発電・送電その他の講義をなさるのですが、研究室では通信工学をしておられ、講義と研究の内容はまるっきり違っておりました。当時はほとんど問題にされなかった通信の研究展開を、八木先生が中心となって東北大学の電気でおやりになっていたのです。いずれにしても、非常な先見の明を発揮されたわけです。その後、通信に関しては、どこにいっても東北大学の卒業生がいる状態になったのです。このように、先見の明をもって大学が発展するよう目指すのが、大学の本当の姿だろうと思っています。
学問は、体系化すると進むものでしょうか。私はむしろ体系化されないうちの方が進むんじゃないかと思います。形が整ってしまうと進まなくなってしまう。東北帝国大学が創られたときには、もともと第二番目が京都帝国大学でございます。京都は、哲学的な学問で大きな成果を収めている訳です。創立からそういう学風で出来ているんですね。
日清戦争のときには大きな賠償金が入ったので、これをかなりふんだんに使って京都大学を創りましたから、今でもかなり残っていますが非常に素晴らしい校舎なんですね。次に三番目と四番目の大学を創ろうというのは日露戦争の後なもんですから、このときは賠償金は一銭もありませんので、内務大臣だった原敬さんが古川家から無理やり寄付を出してもらい、できたのが九州と東北の両帝国大学であります。
開講は九州大学が早いので、あらかた半分以上のお金をつぎ込んでしまいました。その後、札幌農学校を本学の農科大学にするときに、またその半分以上お金を注ぎ込んでしまいました。仙台に来たとき残っていたのは二十万円という金額でした。全部レンガ建てにしようと思ったらお金が足りなくて、木造にしてペンキでレンガの絵を描いたという話がありますが、大体昔から貧乏大学ですね。それもあって、産学協同の知恵がついたのかも
知れません。必ずしも恵まれたところがいいということではなく、恵まれないところで仕事をするというのが大事だと思います。
昔は講座研究費があったんですね。それを巧みに使って仕事をするというのが、この大学の特長かと思います。私の親父は、九州から原龍三郎先生と一緒に東北大学工学部の、応用化学を強化するときに第二陣として赴
任してきたわけですが、
仙台に来て一番嬉しかったの
は、夕方校舎から追い出されない、夜でも電灯がつけられたことだったそうです。
東北大学の一番の特長は、安い研究費で対抗しようと思ったら、学生を相手に測定器械を造りながら新しいことを実験する。これが東北大学の学風であります。そういう意味で、初めからグラスゴ−流の他に見られない非常にユニ−クな成果を挙げた大学である、ということをこれからの若い人たちも誇りに思っていただきたい。
私は卒業研究の指導を、どの先生に受けるかを全然考えていなかったんですが、抜山平一先生がわたしの親父に、「お前の息子はどの先生につくつもりだ」ときかれ「まだ、何も考えていない」といったら、「ちょっとうちへよこしてみなさい」といわれ、伺ったのですが、翌朝抜山先生が私の親父に向かって、「渡辺(寧)さんのところへどうだ」といわれたんですね。そしたら何と先生同志が犬猿の仲なんですね。なぜ仲の悪い渡辺先生のところへやったんだろうと不思議に思っていたら、ある人が、「こんな奴が俺の研究室に来たら、大変だと思ったから、
渡辺先生のところへ入れたんだ
」という話です。その時渡辺研の志望者が二十七人いたんですが、全部入ったんです。
電気と通信を合わせて百人の学生で
す。そのうち二十七人がひとつの研究室に集まったんですが、抜山先生のところには一人も行かないのは失礼だというので、
自ら人身御供になった学生がいるんですね。自民党副総裁の西村さん、松前重義先生、電波管理局長をやった藤木さんとか毎年素晴らしい人材が抜山研を卒業生しているんですね。
これは学生が大人だったこと、先生方が俺のところに何人来たなどというケチな考えをお持ちにならなかったことなどが大きな意味があるんじゃないかと思います。東北大学に入って、誰先生につきたいといった希望を叶えてやることをしないと、本当にその先生につきたい学生は、仙台に来なくなると思います。憧れて大学に来るという風習を、私たちの時代に壊しちゃったのかと非常に残念に思っております。やはり、学生が先生を選ぶというようなことを残しておく方が教育効果が挙がるのではないかと思われます。
昔からそうですね。東北大学に入って本多先生につきたいと思い金属工学科入ったら、
本多先生がおられなかった。先生は物理の先生だから、物理学科に入らないと先生の指導は受けられなかった。間違えて金属工学科に入ったもんだから、退学して受験し直した者もいたんですが、そのまま金属工学科に残った学生もいて、お陰で金属にいい学生がそろったという話もあります。このような風習が、新制になってからなくなって来たという
ことは残念であります。
私は「東北大学百年史外伝」を作ろうと思っております。本編に載らないような面白い話を載せるということで、先生方の原稿を募集いたします。東北大学出版会が出来たんだから、最初の本はお前が出せと言うんです。ただし、原稿料は出せないという、ずいぶんひどい話ですが、「百年史外伝」の方は先生方のご好意に甘えたいと思っております。そのうち、後援会便りなどに私が整理して配布いたしますので、ぜひ面白い、価値のあるお話を出していただきたいと考えておる次第です。以上で終わらせていただきます。(拍手)
[TOP]
|